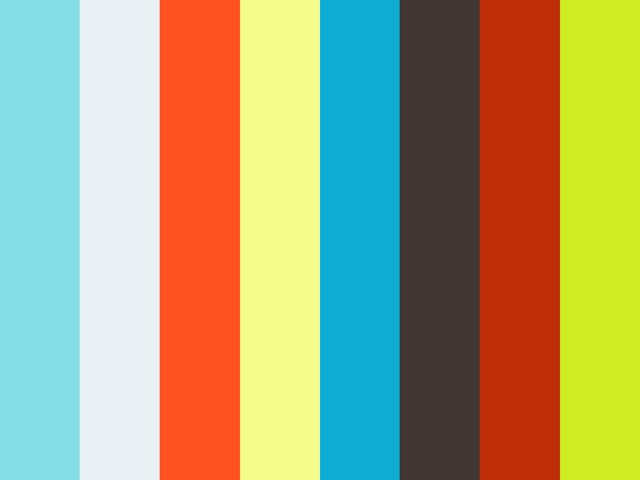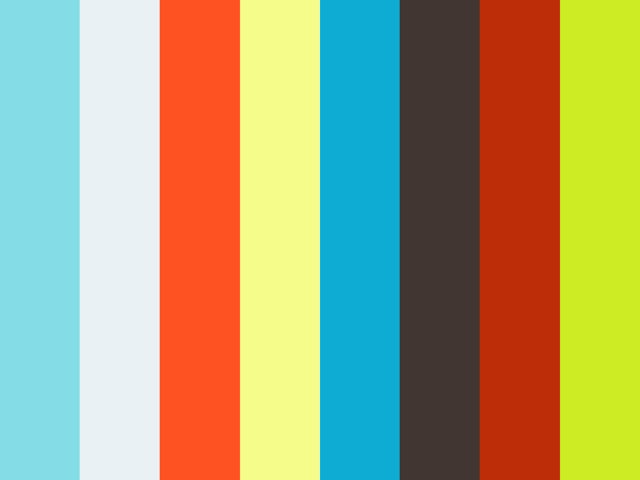これは「やらせ」なのか
NPR (National Public Radio)が、ドキュメンタリー映画監督で、「The Thin Blue Line」や「Fog of War」の監督、エロル・モリス(Errol Morris)氏の本、「Believing is Seeing」(訳し方が難しいね)について紹介している。
この人、映画監督になる前は「写真探偵」と言われるほど写真に対する興味がおありで、歴史に残る写真に隠された「謎」についていろいろと調べるのが好きだったらしい。
番組の中でも取り上げられた本のテーマのひとつが「やらせ」の問題。
「実はあの写真はやらせだったんだよ」と暴露して終わるんじゃなくて、「やらせ(Staging)」とはいったい何なのか、と深い問いかけをしているのがいい。
たとえばクリミア戦争のロジャー・フェントン(Roger Fenton)の有名な写真。丸い大砲の球がゴロゴロしている大地の写真(1855年)なのだが、これがどうも球を集めてきて撮ったものらしいこと。(当時は「爆弾」じゃなくてただの鉄球だからこんなことができたのだろうけど)

Valley of the Shadow of Death by Roger Fenton, 1855
サウスダコタ州の干ばつの大地に置かれた牛の骸骨の写真(1936年)。これも有名な、アーサー・ロススタイン(Arthur Rothstein)が、ルーズベルト大統領の命で行われたアメリカの農村救済のFSAプロジェクトで撮ったもの。この写真も、撮影者が骸骨をどこかから持ってきて、いろいろなところに動かしながら何枚も撮ったものであるらしい。ある人は、ロススタインは骸骨を首都ワシントンから持ち込んだとも言っているそうだ(まさか、そりゃないでしょ)。

Photo by Arthur Rothstein
どっちも写真の歴史の教科書には必ず載ってる有名な写真なのだが、モリス氏が言うのは、これらのフォトグラファーたちは、見た人をあざむこうと思ってこういうことをやったのか、ということ。
さらに、写真はプロパガンダに使われてはいけないというが、どんな写真だってプロパガンダになり得る、それに、true photography, false photographyというものがいったいあるのか?ということなのだ。
これはなかなか深遠な問いかけである。
モリス氏は、そんなことよりも「真実を追求すること(pursue the truth)」がどんなドキュメンタリーでも大切なのだ、と言っている。
起こっていることを撮影したんだから事実でしょ、と逃げるフォトグラファーもいるけれど、そりゃあちょっとずるいと思う。そもそも、客観的写真など存在するだろうか?小さな四角形の中に、フォトグラファーがある時間、ある世界を切り取ったということが、もう主観的なのだ。
さてさて、モリス氏、なんでこんなに写真のウラに興味を持ったのかというきっかけが面白い。2歳の時に父親を亡くしたため、父親の記憶はない。だが、家中に彼の写真があり、彼はこの写真を通して父親を記憶する訳だ。これはいったいどういうことだろう?と考えたのが最初らしい。
「人々は物事を記憶するのではい。写真を通して物事を記憶する」みたいなことをスーザン・ソンタグが言っていたような。(あ、またソンタグ・・・)
と、禅問答みたいになったところで、これ以上やると収集つかないから終わります。