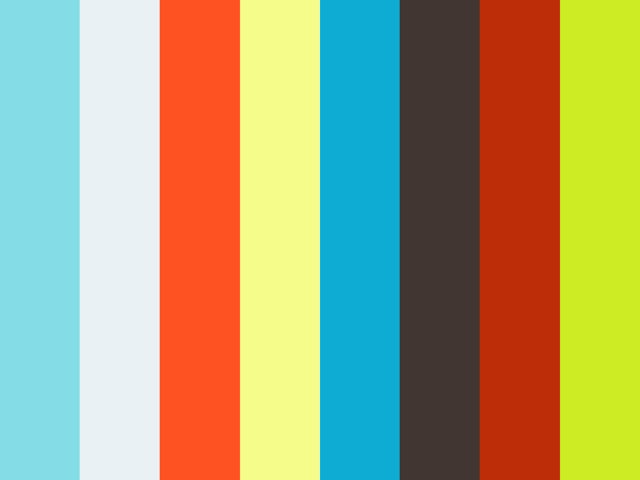これは「やらせ」なのか
NPR (National Public Radio)が、ドキュメンタリー映画監督で、「The Thin Blue Line」や「Fog of War」の監督、エロル・モリス(Errol Morris)氏の本、「Believing is...


911とフォトグラファー 硫黄島写真との相似について
911のiconic(象徴的な)イメージというと、アメリカではこれだろう。 Ground Zero Spirit、などと呼ばれることもあるらしく、世界の多くの新聞、雑誌に紹介され、さらには切手にもなり、この写真に写った三人の消防士は一躍ヒーローとして扱われることになった。...
ボケ考
最近はボケのある写真が流行である。 ボケといっても森山大道の「ブレ、ボケ」ではなくて、一点にピントが合ってあとはボケるという、被写界深度の思いっきり浅い写真のオンパレードと言っていい。アマチュアの間にもこの傾向は顕著で、いかにボケ味のいい写真を撮るかに労力が使われているよう...
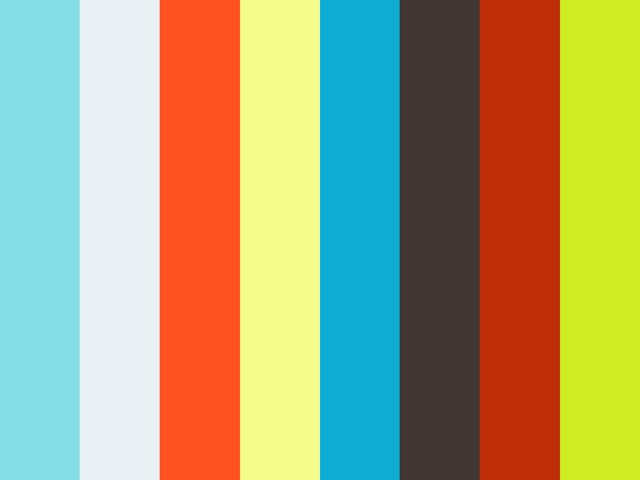
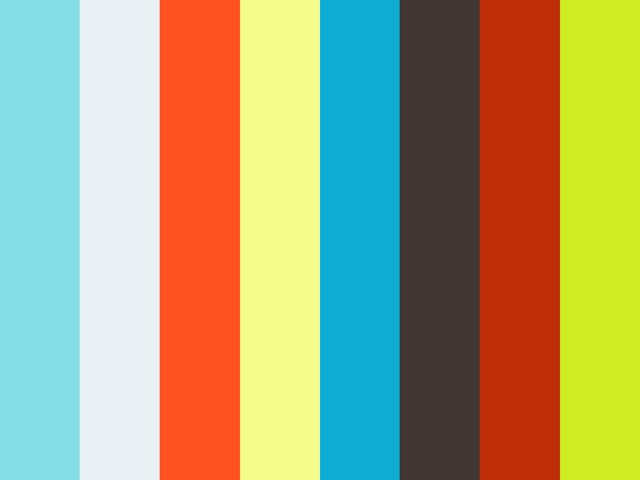
BGM考
いつも愛読させてもらっているRaitankさんのブログに、ニュースフォトグラファーが東日本大震災の被災地の映像を撮影した映像が話題になっている、という記事があった。 (「大震災発生から今日までのアレコレ」 2011/3/23 raitank blog) このビデオです。...