BGM考
- 2011年9月4日
- 読了時間: 7分
いつも愛読させてもらっているRaitankさんのブログに、ニュースフォトグラファーが東日本大震災の被災地の映像を撮影した映像が話題になっている、という記事があった。
このビデオです。
なぜ話題になっているかというと、これがあまりに情緒的であり、あまりに「美しい」からなのだ。そして、情緒的にしているのは、背景に流れている悲しいピアノのBGMによる。 話題になっている、と言ったが要するに、賛否両論なのである。これは何となくわかる。否の方は、こんな悲惨な状況なのに、こんなにきれいな「作品」にしてしまって、どういうつもりだ、ということ。賛の方は、状況が旨にしみた、これをみたうちの子どもは日本の子どもに何か送ろうと活動を始めた、といった具合。 ちなみに、このフォトグラファーはDan Chung氏。調べてみたらイギリスのガーディアン紙のスタッフで、この映像もガーディン紙のコンテンツの一部であるが、なぜかBGM付きは動画サイトのVimeoにアップされたもので、本家のガーディアンはBGM無しだ。Chung氏の国籍は不明だが、イギリスで教育を受けていて、彼のVimeoページにはテクニカルなことを題材にしたビデオクリップが多いので、かなりDSRLに詳しいプロフェッショナルである。 北朝鮮の軍事パレードのスローモーション映像 (North Korean Parade by Dan Chung, Guardian)、というのもあって、これもなかなかのもの。 最近のマルチメディアジャーナリズムのはるか以前から、映像ドキュメンタリーにBGMがあるのは珍しくもないけれど、何で今回のChung氏の映像が批判の対象となるのかを考えてみるのは興味深い。 思うにどうもこれは、内容がストレートニュース(日本の業界用語で言うと「発生モノ」か)に近いほど、製作者がそれに情緒をプラスすることが許されず、フィーチャーモノに近づくと、それが許されるということなのかもしれない。 あるいは、発生から時間があまり経っていない場合はストレートがよくて、発生から時間が経つと編集によって手を加えることが許容されるような気もする。 ストレートニュースといっても、このようなことが話題になるのは、対象が悲惨なものに限る。 では、ストレートニュースでのBGMがそれほど珍しいかというと、そんなことはない。 昭和のニュースフィルムは必ずそのニュースに合せたBGMがあった。今でも民放テレビのニュースショーでは、悲惨な事件にはおどろおどろしいBGMが着く。泣かせるニュースには、ロマンチックなBGMがつく。ラジオはもっと凄い。民放ラジオはストレートの読み上げニュースにもBGMがある。(内容によって変わりはしないが) ついにNHKまでも、天気予報にBGMを解禁した。(たしか2011年からのような気がする)※私はこっちの方が嫌いだけど。 スティルフォトグラファーから、動画の世界にもはまり出して改めて思うのは、「音」の重要性である。 環境音や人の話がきちんと録音できているかどうか、その質によって、コンテンツの訴求力がガラリと変わる。 イメージ50%、音50%と言ってもいい。 そして音楽。これがトドメだ。適切な音楽がかかるとコロッとやられてしまう。 今回のビデオもこれによるところが大きいだろう。Raitank氏も指摘しているように、BGMが無ければこれほどバッシングされることもなかったと思う。 ニュース写真の世界でも、悲惨な状況を撮ったとき、それがあまりに「美しい」と居心地の悪さを感じてしまうことがあるらしい。 あまりに悲惨な状況を目の前にして、フレーミングのこととか、ライティングのこととかを考えながらカメラを構えていること自体が偽善のような気がする、とある写真家が言っていたが、誰だか忘れてしまった。 セバスチャン・サルガドは世界の悲惨な状況を写しながら、そのイメージはたいへん美しく、力強い。 評論家のスーザン・ソンタグは、人間の悲惨な状況と写真での記録について、「他社の苦痛へのまなざし」を著し、このサルガドさえも批判の対象となっている。 では、Chung氏のビデオはどう撮っていたらバッシングされなかったのだろう。 ニュース性とアート性とは相入れないものなのか。それは恐らく、世界のいろいろな文化によって違うのではなかろうか。 日本では、報道写真に芸術性など要らない、という意見が支配的なように思える。少なくとも私が現役とのきはそうだった。芸術性よりも突撃性が重んじられて、とにかくその瞬間を撮ってくればいい、ニュースバリュー、イコール、写真のバリュー、というようなメンタリティーが強かった。 今では、年間の報道写真集の写真などを見ると、ニュースバリューよりも、写真そのもののバリューで語るような写真がけっこうあって、だんだんと変わってきているのを感じるが。 冒頭に戻るが、Chung氏のビデオはあまりに美しかった。 ニュースショーのお涙ちょうだいBGMなら、見る人も「ああそうなのね」と見抜いているのかもしれないが、今回はあまりにBGMと映像の完成度が高く、見る者を客観的にする隙を与えず、感性にぐさりと刺さりこんでしまったのかもしれない。 この感性への働きかけが、マルチメディアジャーナリズムでは革命的といいほど強力だ。だから世界のニュースカメラマンが一気にこの世界になだれ込んできているのではないか、という気がしてならない。 2011/09/09の追記 ソンタグ氏の本のことを書いて、気になって読み返していたらまさに的を得た記述が。 ちょっと長いけど引用。
「変貌は芸術の営為である。しかし不幸や不正の目的証言である写真は、それが「美的に」、つまりあまり芸術的に見えると批判を浴びる。記録を作ることと視覚芸術の作品を生み出すという写真の二重の力は、写真がなすべきこと、なすべきでないことをめぐっていくつかの著しい誇張を生じさせた。最近のもっとも一般的な誇張はこの二つの力を対立するものとしてとらえる態度である。苦しみを描く写真は美しくあってはならないし、キャプションは教訓的であってはならない。このような見方によれば、美しい写真は深刻な被写体から注意を逸らし、それを媒体そのものへと向けさせ、それによって記録としての写真のステイタスを損なう。写真は混じりあった信号を発進する。こんなことは止めさせない、と写真は主張する。だが同時に写真は叫ぶ。何というスペクタクルだろう!と」 (※下線は引用者 『他者の苦痛へのまなざし』スーザン・ソンタグ 北條文緒約 みすず書房 p.74)
そう、そうなのだ。 この、苦しみを描く写真は美しくあってはいけないという説は日本のニュース写真のカルチャーの中に、より強く根付いたものかもしれない。いわゆる「不謹慎」ということだ。今回のChung氏のような映像は日本ではなおさら出現しにくいと思う。
もうひとつ追記。 「あまりに悲惨な状況を目の前にして、フレーミングのこととか、ライティングのこととかを考えながらカメラを構えていること自体が偽善のような気がする、とある写真家が言っていたが」と、上記に書いたが、私の頭にあった「ある写真家」は、ドキュメンタリー写真家のGeorge Rodgerだった。彼が偽善と言ったかどうかはわからないので、その部分は私の思い込み。彼は、ナチスの強制収容所のひとつ、ベルゲン・ベルゼンに解放後初めて入った写真家と言われている。そのときの様子を、こう語っている。 「死者はそこかしこにいた。その数四千におよぶといわれる死体を、構図の整った写真におさめようとしている自分に気付いた。いったいぜんたいわたしはどうなってしまったのか。こんあことがあっていいはずがない。何かがわたしを変えてしまったのだ。世の人々にこのことを伝えるためにも、この情景を写真に撮らねばならない。したがって、わたしとしては何もしないで立ち去ることはできない。そこでわたしは、風景か何かでも撮るように、死体を具合のよう構図におさめ、写真を雑誌社に送った。しかしその時に、戦争写真はもう二度と撮らないと堅く誓い、そのとおりにしてきた。あれが最後だ」 (『フォト・リテラシー』報道写真と読む倫理 今橋映子 中公新書 p.207 ※この部分の原典はRodger氏が1989年にBBCで語ったインタビュー。)
このRodger氏の気持ちは、ニュースフォトグラファーなら誰しも共有する思いなのではなかろうか。 だからといって、それ以来撮るのをやめてしまったRodger氏の判断を称賛するつもりもないし、批判するつもりもない。ニュースフォトグラファーというのは、世間で思われているほどかっこよいものではない。









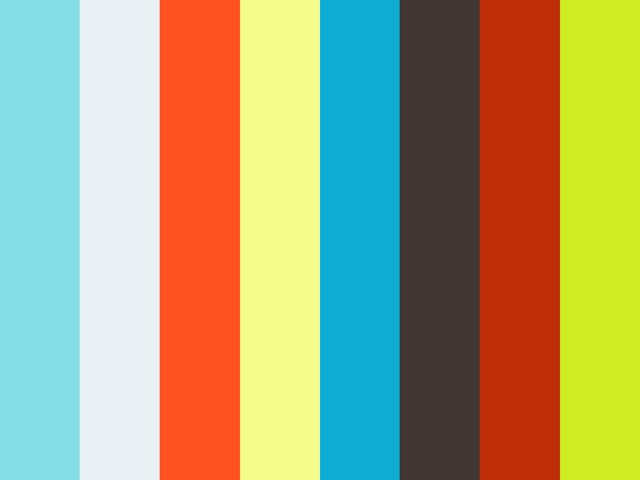
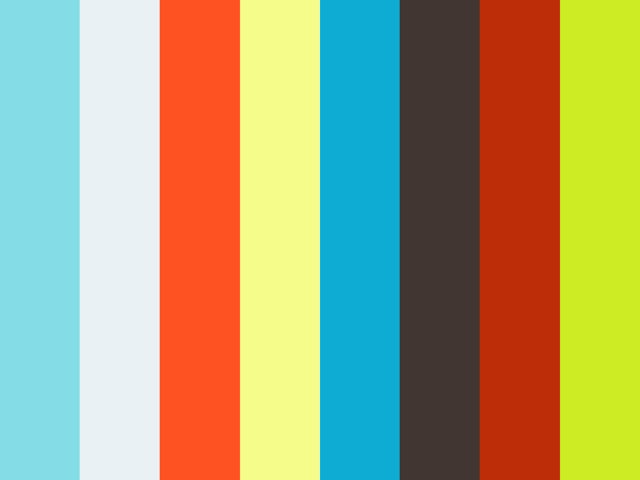










コメント